モデルベース開発
2つのモデル(制御対象と制御器)のモデルを各開発フェーズで使い効率化、製品の品質向上を図る手法として現在色々な分野に普及している。2つのモデルを机上検討のみならず、実機の制御やシステムの検証に使うことにより効率化を図る事ができる。 JMAABの上げているMBDのメリットは次の4つである。
- モデルとして見える
- モデルが動く
- モデルを共有できる
- 自動化できる
モデルベース開発は1970年代より進化しながら現在にいたっているがその歴史について文末にまとめた。 今の業界の状況から自分の立ち位置を確認できると思われる。
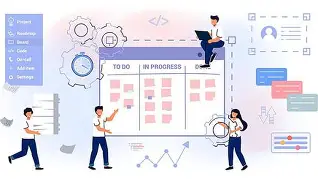
プロセス統合(既存プロセス or 新規プロセス?)
多くの場合すでに確立された開発プロセスが存在しており、新規にモデルベース開発を導入するにはかなりの工数が必要になると予想されます。 導入には導入時の工数と今後予想される工数を見積、最適な導入を図りましょう。 メリット・デメリット双方が同じ程度と見積もられる場合には将来の姿を想像する事でおのずと解がみつかると思われます。
モデルベース開発歴史
🔹 モデルベース開発(MBD)の歴史概要
1. 黎明期(1970〜1980年代)
- 背景:制御工学とシミュレーション技術が進展し、数値解析やシステム同定の研究が活発に。
- MATLAB(MathWorks, 1984)の登場により、制御系設計を数値的に扱えるようになった。PC版が出たことで、その利用が加速的に進んだ。
- 当時は主に研究開発用途(航空宇宙・自動車の一部)で利用。
2. 拡大期(1990年代)
- Simulink(1990年代初頭) の登場で、ブロック線図による直感的なモデリングとシミュレーションが可能に。
- モデルを中心にシステム設計 → 実機試験前に挙動を予測 という考え方が浸透。
- 自動車産業では、エンジン制御、トランスミッション制御などに適用が始まる。
3. 産業実装期(2000年代)
- 自動車、航空宇宙、産業機械でECU(電子制御ユニット)開発が急増。
- MBDはソフトウェア開発工程を効率化する手法として急速に普及。
- MIL(Model-in-the-Loop)
- SIL(Software-in-the-Loop)
- HIL(Hardware-in-the-Loop)
などの段階的な検証手法が体系化。
- ISO 26262(自動車の機能安全規格)とも関連し、品質保証の観点からも注目。
4. 高度化・普及期(2010年代〜現在)
- 自動運転、電動化、eVTOLなどの複雑システムに対応するため、MBDは必須の開発基盤に。
- デジタルツインやAIとの融合が進み、リアルタイムでの最適化・予測に活用。
- ツールチェーンの拡大(Simulink, Dymola, AMESim, Modelicaなど)。